鮎を知る

鮎を知っているのは食べたことがあるだけと言う方もいます。ヤナと言われるところで落ちてくる鮎を手づかみし、塩焼きにすれば本当においしいです。
さて、鮎を釣るためには鮎の習性や生態をある程度知っておくと役に立ちます。
鮎しゃくりをやってた頃、アユは人が下流に向かって移動すると上流に移動し、人が上流に移動すると鮎は下流に流れます。
流れのことを考えると下流に下る鮎の速さより登っていく鮎の速さが幾らか遅くなります。その習性ををうまく利用してしゃくり竿で狙いを定めつつ自分の体を下流に下らせて鮎が登り始めたところをしゃくります。
この習性は、ポイントからいったん遠ざかった野アユをオトリの近くまで戻らせるためにポイントにオトリを止めておいて、なおかつ自分が少しづつ上流に歩くことにより野アユはオトリがいるところまで下ってくるのです。
アユの縄張りと闘争本能

鮎と言う魚の一番の特徴は縄張りをもち、守ろうとする闘争的な習性です。
この闘争本能を誘って釣る方法が友釣りで、アユならではの釣り方といえます。
アユの生態 (中公新書 505)
小さい時はプランクトンや水の中の昆虫を食べて成長していきます。水生昆虫を食べているときにはドブ釣りという釣りが有効になります。
さらに成長すると石アカ(藻)を食べるようになり、石アカを確保するために、なわばりを作り始め、なわばりに入ってくるアユを追い払うようになります。
なわばりはの範囲は大体左右前後1メートルくらいです。
なわばりを作らず群れと一緒に行動しているのは「遊びアユ」「鮎玉」と言われるものもある

たいてい遊びアユは闘争性を持たないので群れていたとしても友釣りには向かない闘争性は、天然遡上アユ、湖産アユ、によっても違いがある。湖産アユのほうが闘争性は強い。
アユ その生態と釣り―アユのすべてがわかる本 (アングラーズサイエンス)
鮎・アユの体
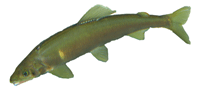
アユのオスとメスの違いは産卵期に特徴が出てくる。尻ビレでくぼんだ形をしているのがメス。産卵期にはメスをおとりにしたほうが掛かりが良くなる。
写真はメス。尻ビレが前のほうが高くなっていて尾のほうに近づくにつれてくぼんだ形になっている。
オスは産卵期には背の部分が黒い感じが出てきます。胴回りは橙色の婚姻色が表れることになります。
板取川の鮎
岐阜県関市の板取川は透明度は落ちてきているもののまだまだ水中撮影でも十分先の鮎まで捉えられる。